【聖母愛児園のPR】
◆子ども一人ひとりの個性に合わせた「個別支援」の徹底「当園では、一人ひとりの子どもたちを大切にする『ケア的養育(太陽の支援)』に力を入れています!」
例えば、ルールや指導・罰則などを重視するのではなく子どもに寄り添い耳を傾け、対話をしていく養育のことで、本来家庭で感じるはずだった「当たり前」の安心・安全な生活と職員ら大人たちとの信頼感を育む養育を推奨しています。
特に不登校児への支援においては、子どもたちが抱える様々な問題に対して、職員一丸となって解決に導く体制が整っています。
◆業務効率化を徹底する「IT化」
職員が子どもたちと向き合う時間を最大化するため、最新のITツールを活用した業務効率化を進めています。情報共有ツールを導入し、例えば、システムの中に子どもの起床・就寝時間や食事量、服薬状況などのあらゆる情報を一元管理できるようにすることで、「最近、この子が不調な理由はなんだろう?」と疑問が出た際に直近の睡眠時間が短いためか、食事量が足りてないためかなど原因を見立てる際の情報収集をスピーディにできるようにし、1秒でも多く子どもと関わる時間が確保できるよう工夫をしています。
◆職員の「向上心」に応える独自の研修制度
外部の研修機会が減る中でも、職員の成長意欲を支えるため、約5年前から独自の「まかな研修」を実施しています。これは、外部研修では扱われない題材ではあるものの、現場の職員が「実は気になっていた」「あったら嬉しい」と感じるテーマ(子ども達の自立、調理について、横浜市中区を知ろう!など)を施設内の職員が講師となって行うユニークな研修です。
【児童構成】
[本体施設]定員80名・すべて男女混合縦割り
A棟:2ホーム(各8名定員)
B棟:4ホーム(各8名定員)
C棟:4ホーム(各8名定員)
[地域小規模児童養護施設]
12名
本郷ホーム:6名定員・男女混合縦割り
千代崎ホーム:6名定員・男子のみ縦割り
特徴的なのは、ほとんどのホームが男女混合で縦割りなので幼児〜高校生が幅広く同じホームで生活をするスタイルであることです。最高で年齢差が16歳の子ども達が衣食住をともにする形態は他施設でも珍しい光景だと思います。
2024年度から当園を18歳で卒園された利用者が生活できる「児童自立生活援助事業Ⅱ型(通称:自立サポートホーム)」を開設しました。
【聖母愛児園の外観】
[正門から見た外観]

[建物の裏手にある園庭]

【聖母愛児園の内観】
[ホームのリビング]

[ホームの児童居室]

[ホームの宿直室(スタッフルーム)]

【運営理念】
家庭的な生活環境の中で家庭的な養育を推進し、子ども達と職員が共に育み、互いに愛し、一般的な家族の概念を超えた、神の家族として成長していくことを基本理念としています。【聖母愛児園の行事】
[おうちで旅行]

[県内施設対抗の野球大会に向けた練習の様子]

[礼拝行事の様子]

[礼拝では出し物をやることもあります!(職員バンドの様子)]

[礼拝には絶品のごちそうも並びます!]

当園では各ホームでの旅行・外出をケア的養育の観点から重視しています。
そのため、施設全体での行事は極力行わず、進級入学・卒業卒園・七五三・クリスマスなど、節目となる時期に礼拝を行っています。
また、県内施設対抗の野球・ソフトボール、団体主催のイベントに参加しています
年間通して礼拝やホーム旅行、季節の行事(餅つき大会、お花見、スキー旅行)などイベントが充実しています。
【聖母愛児園で働いている職員・仕事環境】
<職員構成>職員数:全体の職員数:約60名
うちケアワーカー:約43名
<職場の雰囲気>
子ども達の自立支援をしたいとの思いで入職してくる職員が多いです。
個々の人格を尊重しつつチームワークを大切にしています。
<勤務体制(直接処遇職員)>
・通勤方法:通い(マイカー通勤可)
・職員寮あり(単身向け・家族向け)
・1ヶ月の宿直回数:5回程度
・年間休日日数:114日
・年次有給休暇:入職後半年で10日付与
・勤務時間例
A1:06:00-14:00
A2:07:00-15:00
B(宿直):15:00-24:00
宿直明け1:06:00-12:00
宿直明け2:07:00-13:00
日勤:09:00-17:00
※外部会議・学校行事等、状況に応じて断続あり
<福利厚生>
雇用労災保険・健康保険・厚生年金・福祉医療機構退職金共済・横浜市社会福祉協議会年金共済
<研修・人材育成>
園内研修(まかな研修)
外部研修
チューターチューティー制度※1を導入して人材育成をしており先輩・後輩で意見交換が気軽にできる環境です。
※1:チューターとは新入社員(もしくは若手社員)の指導者のこと。主に先輩職員が務める事が多い。チューティは指導を受ける新入社員のことを指す。
<こんな人を待っています!>
「ケア的養育には、多くの「専門的知識」が必要です。子どもたち一人ひとりを理解し、自ら考えて、その子一人ひとりにどの様な支援が必要かを考えて支援しなければならないからです。」
そこで聖母愛児園ではこんな人に来てもらいたいです!
・専門性を持って働きたい人
・施設の方針(ケア的養育)に賛同できる人
・他者批判をせず、協調性のある人
※もちろん初任からプロであれとは言いません。専門性の高い先輩たちに教わりながら『プロでいようとする姿勢』を持てる方に来て欲しいです。



.jpg)
.jpg)



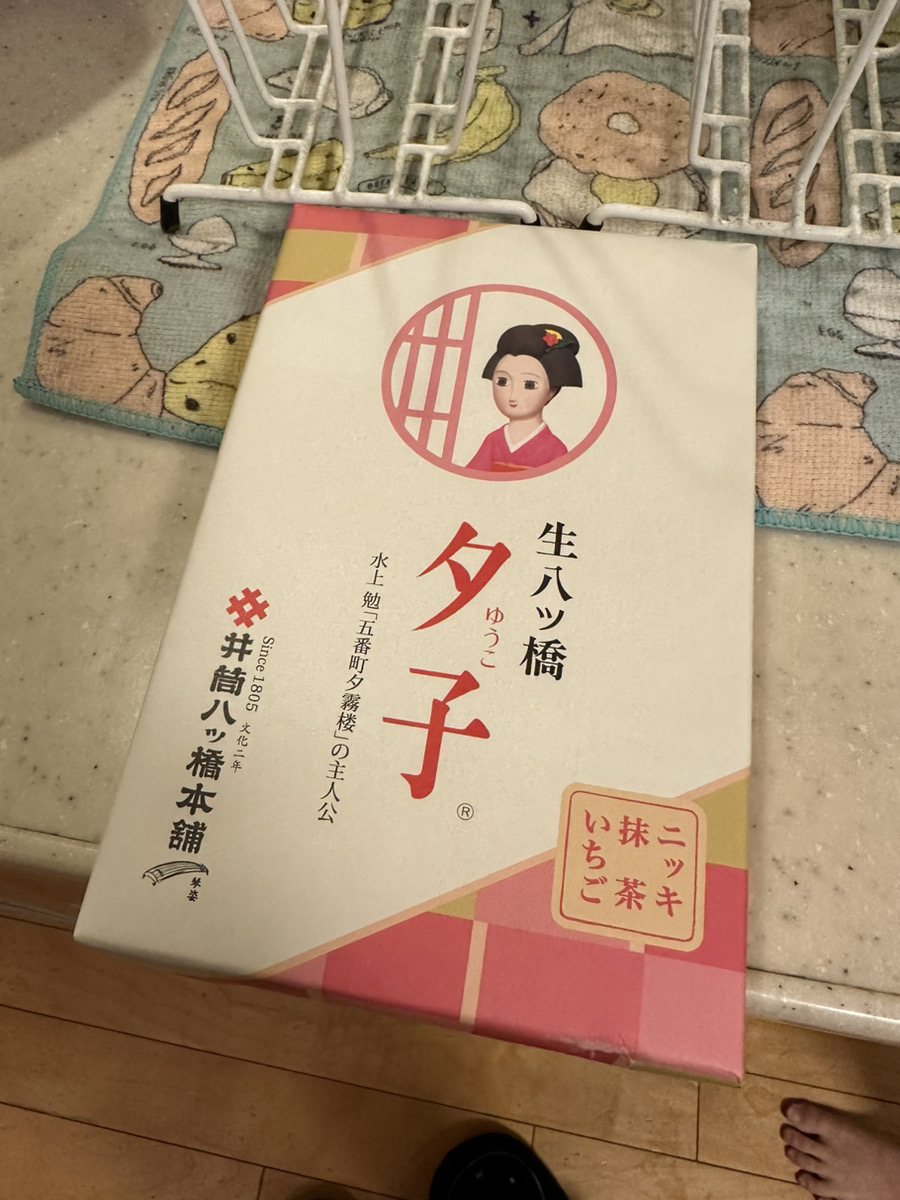
.png)
.jpg)

