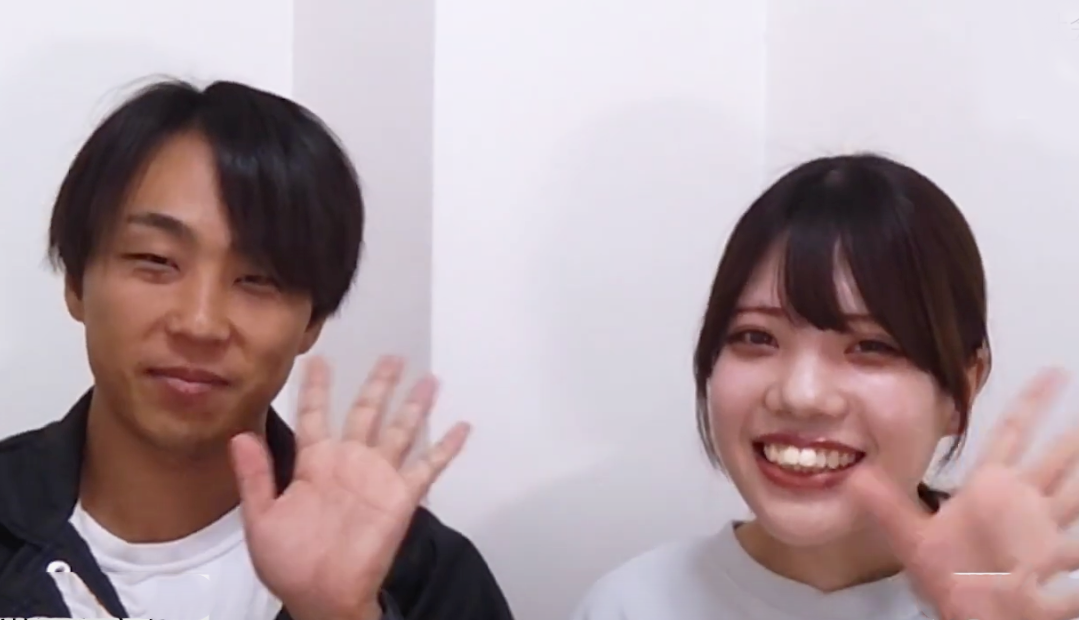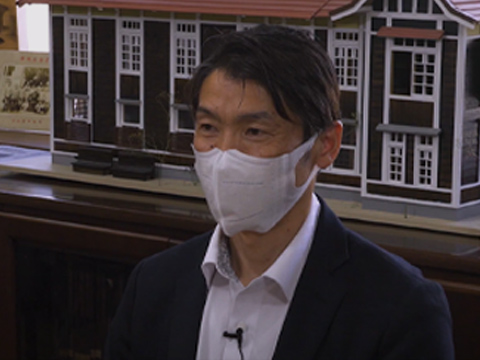海の子学園 入舟寮 山川 樹里さん・上田 茉奈花さん

目次
自己紹介をお願いします。
(上田茉奈花さん)大阪市 児童養護施設の入舟寮の上田茉奈花です。
(山川樹里さん)同じく入舟寮の山川樹里です。
(上田さん)2年目です。
(山川さん)同じく2年目です。
(山川樹里さん)同じく入舟寮の山川樹里です。
(上田さん)2年目です。
(山川さん)同じく2年目です。
所属ユニットは?
(上田さん)私は高学年の小規模のうみつばめホームで働いています。高校2年生が3人いて、中学3年生がひとり、中学2年生の子がひとり、中学1年生の子がひとりの、合わせて全員で6人です。
(山川さん)私は幼児ホームの職員をしています。年齢は3歳から6歳の男女を見ています。
(山川さん)私は幼児ホームの職員をしています。年齢は3歳から6歳の男女を見ています。
児童養護施設で、働こうと思ったきっかけは?
(上田さん)私が大学2年生の時に、社会福祉士の実習で京都の方の児童養護施設に実習に行かせてもらったんですけど、そこの施設は全部が小規模で、すごく一人ひとりに時間をかけてこどもたちを見ているっていうところを長い期間宿泊で見させてもらって、私もこんなふうにこども一人ひとりに大きく時間を割ける仕事をしてみたいなと思って、児童養護施設に就職することを決めました。
(山川さん)私は児童養護施設に働こうと思った理由は、まずこどもと関わりたいっていうのが大きくて、保育士、保育園、幼稚園、施設で悩んだ時に、私の性格上、できるできないを見てた時に、幼稚園保育園は働きづらい、長く続けられないな、でもこどもと関わりたいなっていうのを思って先生に相談したら施設があるよっていうのを紹介していただいて、施設にしようって決めました。
(山川さん)私は児童養護施設に働こうと思った理由は、まずこどもと関わりたいっていうのが大きくて、保育士、保育園、幼稚園、施設で悩んだ時に、私の性格上、できるできないを見てた時に、幼稚園保育園は働きづらい、長く続けられないな、でもこどもと関わりたいなっていうのを思って先生に相談したら施設があるよっていうのを紹介していただいて、施設にしようって決めました。
入舟寮を選んだ理由は?
(上田さん)先ほども言ったんですけど、実習ですごく小規模だったんですけど、その小規模っていうところにすごいこだわりが自分の中であって、海の子学園は小規模を進めていってる施設でもあるので、やっぱり小規模の施設があるところに行きたいっていう気持ちがすごいあったので、実際に施設見学に行かせてもらって、小規模とか最初の方の施設を見させてもらって、すごく雰囲気がよかったので、ここで働いてみたいなっていうのをすごく思いました。
(山川さん)入舟寮に見学くるまえに、いろんな施設を見学をしていて、3、4施設を見てたんですけど、私に合う、働きたいって思う施設がなくて、またこれも先生に相談してたらこの入舟寮があるよって言ってくれて、見学に行った時に職員の温かさとか、こどもたちが何も言わず、でもおはようとかこんにちはって言ってくれる姿を見て、ああ、この施設いいなと思ってここに決めました。
(山川さん)入舟寮に見学くるまえに、いろんな施設を見学をしていて、3、4施設を見てたんですけど、私に合う、働きたいって思う施設がなくて、またこれも先生に相談してたらこの入舟寮があるよって言ってくれて、見学に行った時に職員の温かさとか、こどもたちが何も言わず、でもおはようとかこんにちはって言ってくれる姿を見て、ああ、この施設いいなと思ってここに決めました。
この仕事の大変なところや嬉しかったところは?
(山川さん)1年目の時に入職してすぐ、幼児ホームの男の子に新しい先生は触らないでとか、新しい先生とは遊びたくないっていうことをすっごい言われて、その時はグサってくるし、もうどうしようみたいな感じだったんですけど、日々関わっていく中で、その子が一緒に遊ぼうとか、一緒にこれしようとか、これ見てとか、こう言ってくれた時は、すごいこう長く頑張って諦めず関わり続けて良かったなって思います。
あと2年目になってからは、高学年の子と関わることが増えて、アルバムを見てよとか、お母さんこんなんでなとか、思い出話をたくさんしてくれて、関係性ができてきてるんだなっていうのを、続けててよかったなと思います。
(上田さん)私のホームは中学1年生の子がいるんですけど、やっぱりすごい落ち着かなくなったりとか、パニックになることがすごい多くて、どんな時かって言ったら、やっぱり何か自分が思ってるのが違ったりとか、予定が変更されたりするのがすごく苦手な子で、そうなるたびにパニックになってしまうんですけど。その度に本人と話をするんですけど、私もぐわっと言われてしまうと、ちょっとひるんでしまったりとか、私自身もイライラしてしまって言い返してしまったりとか、そんな中でも本人が言われたくないこととかを私がイライラしてしまって、パッて言っちゃった時とかは、職員として失格だなっていうのをすごく感じて。不甲斐なさとかもあって、かなりしんどかったんですけど、でもその度に本人とその話をしていくなかで、やっぱりこういう時こうした方が良かったよねっていうところ、最後にはもうお互いにごめんねっていうところを言えると、やっぱりまた関係性が深まったりとか、その後の日常生活も落ち着いて過ごせるんだなっていうところはあるんですけど。でもやっぱりパニックになる子には初めて私も児童養護施設に来て関わるので、どうしたらいいかわからないことがすごく多くて、それはかなりしんどかったかなっていうのを思います。
あと2年目になってからは、高学年の子と関わることが増えて、アルバムを見てよとか、お母さんこんなんでなとか、思い出話をたくさんしてくれて、関係性ができてきてるんだなっていうのを、続けててよかったなと思います。
(上田さん)私のホームは中学1年生の子がいるんですけど、やっぱりすごい落ち着かなくなったりとか、パニックになることがすごい多くて、どんな時かって言ったら、やっぱり何か自分が思ってるのが違ったりとか、予定が変更されたりするのがすごく苦手な子で、そうなるたびにパニックになってしまうんですけど。その度に本人と話をするんですけど、私もぐわっと言われてしまうと、ちょっとひるんでしまったりとか、私自身もイライラしてしまって言い返してしまったりとか、そんな中でも本人が言われたくないこととかを私がイライラしてしまって、パッて言っちゃった時とかは、職員として失格だなっていうのをすごく感じて。不甲斐なさとかもあって、かなりしんどかったんですけど、でもその度に本人とその話をしていくなかで、やっぱりこういう時こうした方が良かったよねっていうところ、最後にはもうお互いにごめんねっていうところを言えると、やっぱりまた関係性が深まったりとか、その後の日常生活も落ち着いて過ごせるんだなっていうところはあるんですけど。でもやっぱりパニックになる子には初めて私も児童養護施設に来て関わるので、どうしたらいいかわからないことがすごく多くて、それはかなりしんどかったかなっていうのを思います。
入舟寮で役立った研修などは?
(山川さん)私はCOSP※を受けて良かったなって思っていて、その理由としては、子育ては3割できてればいいみたいな、COSPで習って、私はもう全部10割できないと失格やって最初思ってたので、3割でいいやって思うと、ここ失敗してもここでカバーできればというか、なんかこう心が楽になりました。その3割でいいよっていうのを聞いて、そんな完璧じゃなくていいんやなっていうことを学べました。
※COSP:安心感の輪プログラム(Circle of Security Parentingの略)
(上田さん)私は機中八策※っていう研修があったんですけど、機中八策って研修ではこどもたちが例えば悪いことをしてしまった時とかに、職員もやっぱり悪いことしてしまうと、そのまますごい強い口調で怒ってしまったりとかしちゃうんですけど、そうではなくて、何か優しい言葉で。やっぱり強い言葉で言うと、こどもたちもひるんでしまうというか、傷ついたりすることもあるので、そういう時に機中八策を使って、その、例えば大きく言ったら窓ガラスを割ってしまったとかだったりしたら、そういう時にバーッて怒るんじゃなくて、じゃあこういう時どうすればよかったかなっていう、その子の代わりの行動、イライラしてしまった時に窓ガラスを割るんじゃなくて、その代わりの行動、例えば部屋に入ればよかったよねとか、そういうところを代わりの行動を示してあげて、それが次につながってイライラした時にきちんと部屋に行けたら、それをちゃんと褒めてあげるとかっていうのが機中八策の研修で習って。私のホームでは発達障害の子も多いので、口で言うだけでは伝わらないことが多いので、簡潔にじゃあこういう時どうすればよかったっていうのを聞いてあげて、こうすればよかったっていうので返ってきたら、じゃあ次からそうしてみようねっていうところをお話しして、次からできるようになったら、こどもたちの成長とかもすごい感じれるし、ちゃんと話聞いてくれてるんだなっていうのをすごい感じて、受けて良かったなっていうのを思います。
※「機中八策」は千葉県の児童相談所長(渡邉直氏)が考えた、こどもとのスムーズな対話術です。
※COSP:安心感の輪プログラム(Circle of Security Parentingの略)
(上田さん)私は機中八策※っていう研修があったんですけど、機中八策って研修ではこどもたちが例えば悪いことをしてしまった時とかに、職員もやっぱり悪いことしてしまうと、そのまますごい強い口調で怒ってしまったりとかしちゃうんですけど、そうではなくて、何か優しい言葉で。やっぱり強い言葉で言うと、こどもたちもひるんでしまうというか、傷ついたりすることもあるので、そういう時に機中八策を使って、その、例えば大きく言ったら窓ガラスを割ってしまったとかだったりしたら、そういう時にバーッて怒るんじゃなくて、じゃあこういう時どうすればよかったかなっていう、その子の代わりの行動、イライラしてしまった時に窓ガラスを割るんじゃなくて、その代わりの行動、例えば部屋に入ればよかったよねとか、そういうところを代わりの行動を示してあげて、それが次につながってイライラした時にきちんと部屋に行けたら、それをちゃんと褒めてあげるとかっていうのが機中八策の研修で習って。私のホームでは発達障害の子も多いので、口で言うだけでは伝わらないことが多いので、簡潔にじゃあこういう時どうすればよかったっていうのを聞いてあげて、こうすればよかったっていうので返ってきたら、じゃあ次からそうしてみようねっていうところをお話しして、次からできるようになったら、こどもたちの成長とかもすごい感じれるし、ちゃんと話聞いてくれてるんだなっていうのをすごい感じて、受けて良かったなっていうのを思います。
※「機中八策」は千葉県の児童相談所長(渡邉直氏)が考えた、こどもとのスムーズな対話術です。
入舟寮の良いところは?
(山川さん)入舟寮の良さはOJT研修とかCOSPをみんなで受けてるので、ある一定の共通言語とか理解が一定にあるので、こどもを支援とか養育していく中でズレがそんなに大きくないっていうのがいいところなのかなって、この仕事のやりやすさでもあるし、いいところなのかなと私は思います。
(上田さん)私自身で働いていく中で、入舟寮に良さを感じるなと思ったのは、やっぱりこどもたちがすごい優しいところですかね。働いていく中でも、すごい自分ができなかったこととか、例えば私、料理がすごい苦手なんですけど、こどもたちが手伝ってくれたりとか、できなかったことに対して責めるんじゃなくて、一緒にやってくれるっていうところがすごい優しいなって思ったりとか、困ってたらすぐ助けてくれるこどもたちばかりで。働いていて、職員の優しさもすごく感じるんですけど、やっぱりそういう優しい職員の人たちに育ててもらってるこどもたちは、もっと優しく育ってて、すごい働いてて温かい気持ちになることが多いです。
(上田さん)私自身で働いていく中で、入舟寮に良さを感じるなと思ったのは、やっぱりこどもたちがすごい優しいところですかね。働いていく中でも、すごい自分ができなかったこととか、例えば私、料理がすごい苦手なんですけど、こどもたちが手伝ってくれたりとか、できなかったことに対して責めるんじゃなくて、一緒にやってくれるっていうところがすごい優しいなって思ったりとか、困ってたらすぐ助けてくれるこどもたちばかりで。働いていて、職員の優しさもすごく感じるんですけど、やっぱりそういう優しい職員の人たちに育ててもらってるこどもたちは、もっと優しく育ってて、すごい働いてて温かい気持ちになることが多いです。
就活生の皆さんにアドバイスは?
(山川さん)アドバイスになるかわからないんですけど、私はこうやった方がよかったのかなって思うのは、どこの年齢に配属されるかわからないので、ちょっと難しいかもしれないんですけど、今の流行りとか、このちっちゃい子は何のアニメを見てるとか、何のカードゲームが好きとか、どんなルールがあってとかいうのを一つ知っておくと、こどもとの関わりやすさができるのかなと思うので。この流行りを一つ知る、遊びを一つ知っておく、得意技を増やしておく、今のうちにしてたらいいのかなって思います。
(上田さん)入舟寮にぜひ来てください。
(山川さん)待ってます。
※撮影当時の情報です
(上田さん)入舟寮にぜひ来てください。
(山川さん)待ってます。
※撮影当時の情報です
施設概要

入舟寮(いりふねりょう)は大阪メトロ中央線の朝潮橋から歩いて8分の所にある児童養護施設です。
港区内に「入舟寮」と「池島寮」の2つの児童養護施設があり、同じ幼稚園・小学校・中学校に通っています。昔から施設を理解してくれる地域の方々に支えられて生活をしています。
艀(はしけ)労働者のお子さんをお預かりする施設として昭和24年に発足し、後に児童養護施設となりました。平成31年に地域小規模児童養護施設「うみつばめ」を開設し、より地域と密着した運営を行っています。また令和6年4月から地域小規模児童養護施設「うみすずめ」と「あおさぎ」を同時に開設しました。
当施設の最大の特徴は…
①23組の週末里親を始めとしてボランティアのサポートが多いこと。週末里親の数は近畿圏の児童養護施設でもトップクラスです!
②クラブ活動や行事が多く、子どもたちが生き生きと活動をしているところ。子どもたち主体の活動により自己肯定感の向上や、困難を乗り越えていく力を育むことに役立っています。
③学校のクラブ活動や習い事・塾への参加もでき、育ちの中で「失敗を恐れずリカバリーする力」を身につけています。
④職員研修の制度が整っていること。アタッチメントをベースにした研修COS-P(サークル・オブ・セキュリティー・プログラム)を年間通じて取り組むことで、子どもたちの養育にも役立てています。
⑤職員の子どもたちへの思いが熱いところ!! 子どもたちのために熱心な職員が多く、子どもたちと楽しみながら行事の運営・スポーツ活動・アフターケアなどにも意欲的に活動・活躍しています。
⑥アタッチメントとライフストリーワークには力を入れている。その取り組みが評価され「NHKハートネットTV」他でも取り上げられた。詳しくはホームページをご覧ください。
⑦研究熱心な職員が多く、児童虐待防止学会(Jaspcan)、ライフストーリーワーク全国交流会、全国児童養護施設協議会セミナーなどでも発表・報告をして研鑽を深めている。
港区内に「入舟寮」と「池島寮」の2つの児童養護施設があり、同じ幼稚園・小学校・中学校に通っています。昔から施設を理解してくれる地域の方々に支えられて生活をしています。
艀(はしけ)労働者のお子さんをお預かりする施設として昭和24年に発足し、後に児童養護施設となりました。平成31年に地域小規模児童養護施設「うみつばめ」を開設し、より地域と密着した運営を行っています。また令和6年4月から地域小規模児童養護施設「うみすずめ」と「あおさぎ」を同時に開設しました。
当施設の最大の特徴は…
①23組の週末里親を始めとしてボランティアのサポートが多いこと。週末里親の数は近畿圏の児童養護施設でもトップクラスです!
②クラブ活動や行事が多く、子どもたちが生き生きと活動をしているところ。子どもたち主体の活動により自己肯定感の向上や、困難を乗り越えていく力を育むことに役立っています。
③学校のクラブ活動や習い事・塾への参加もでき、育ちの中で「失敗を恐れずリカバリーする力」を身につけています。
④職員研修の制度が整っていること。アタッチメントをベースにした研修COS-P(サークル・オブ・セキュリティー・プログラム)を年間通じて取り組むことで、子どもたちの養育にも役立てています。
⑤職員の子どもたちへの思いが熱いところ!! 子どもたちのために熱心な職員が多く、子どもたちと楽しみながら行事の運営・スポーツ活動・アフターケアなどにも意欲的に活動・活躍しています。
⑥アタッチメントとライフストリーワークには力を入れている。その取り組みが評価され「NHKハートネットTV」他でも取り上げられた。詳しくはホームページをご覧ください。
⑦研究熱心な職員が多く、児童虐待防止学会(Jaspcan)、ライフストーリーワーク全国交流会、全国児童養護施設協議会セミナーなどでも発表・報告をして研鑽を深めている。
求人情報

児童養護施設 児童指導員(正職員)募集!2026年(R8.4 .1~採用)
-
海の子学園 入舟寮
-
大阪府大阪市港区池島3-7-18
-
自立支援やアフターケアに注力|先駆的・独自の取組みがある|職員が意見を言いやすい職場
- 賞与年2回
- 宿直手当あり
- 扶養手当あり
- 住宅手当あり
- 通勤手当あり
- 退職金あり
- 産休あり
- 育休あり
- 異動なし
- 有給あり
入舟寮(いりふねりょう)は大阪メトロ中央線の朝潮橋から歩いて8分の所にある児童養護施設です。 港区内に「入舟寮」と「池島寮」の2つの児童養護施設があり、同じ幼稚…

児童養護施設 保育士(正職員)募集!2026年(R8.4.1~採用)
-
海の子学園 入舟寮
-
大阪府大阪市港区池島3-7-18
-
自立支援やアフターケアに注力|先駆的・独自の取組みがある|職員が意見を言いやすい職場
- 賞与年2回
- 宿直手当あり
- 扶養手当あり
- 住宅手当あり
- 通勤手当あり
- 退職金あり
- 産休あり
- 育休あり
- 異動なし
- 有給あり
入舟寮(いりふねりょう)は大阪メトロ中央線の朝潮橋から歩いて8分の所にある児童養護施設です。 港区内に「入舟寮」と「池島寮」の2つの児童養護施設があり、同じ幼稚…