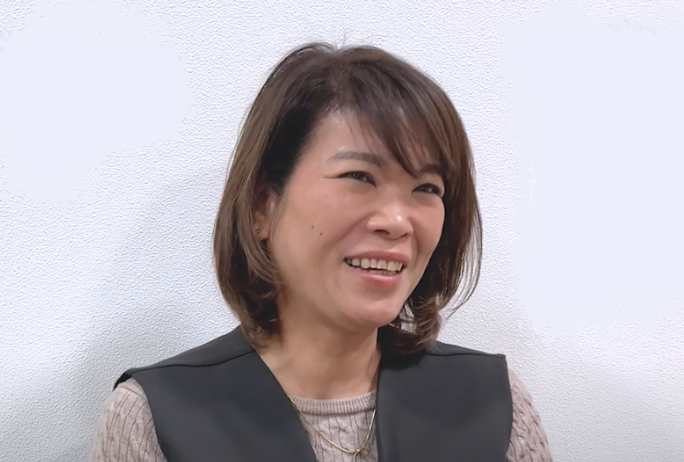自立援助ホーム 子供の家 安西 陵 さん

自己紹介をお願いします。
兵庫県にあります神戸市立自立援助ホーム 子供の家で男子担当のリーダーとして仕事をしております。安西陵といいます。よろしくお願いします。今は勤続して5年目になります。
自立援助ホームで、働こうと思ったきっかけは?
まずは児童養護施設の神戸真生塾の方に入社をしたいという気持ちがありまして。学生時代の頃に経験した実習で、ちょうど神戸真生塾での実習をさせていただいたときに、すごく家庭的だったんですよね。それまでに行っていた実習の保育園であったり、幼稚園であったり、結局はみんな、保育所に来てお家に帰るっていう所だったんですけれども、児童養護施設はそこが帰る場所、そこが生活する場所というところにすごくアットホームさを感じて、神戸真生塾で働きたいと思って、神戸真生塾の方で勤めさせていただきました。その後、今の自立援助ホームの施設長の方から、自立援助ホームでも経験を積まないかということでお声がけをいただきまして、子供の家に来ることになりました。
私も児童養護施設では高年齢児の男の子を見てたのもありましたので、そこまで抵抗というか戸惑いはなかったんですけれども。ただ、自立援助ホームはこどもたちが外に働きに出て、ホーム費を入れて、そこから自立を目指すっていうところなので。それをすごく短いスパンで、児童養護施設であれば10年以上という時間をかけるこどももいるんですけれども、自立援助ホームではそれが2年3年、もっと早いこでは半年という中でのスピーディーさは求められるなというところでの入職してからの目まぐるしさにはちょっと戸惑いました。
そうですね、平均で年々入所の時期は長くなってきています。平均すると、1年から1年半ぐらいが平均で退所の時期っていうのは来ています。
私も児童養護施設では高年齢児の男の子を見てたのもありましたので、そこまで抵抗というか戸惑いはなかったんですけれども。ただ、自立援助ホームはこどもたちが外に働きに出て、ホーム費を入れて、そこから自立を目指すっていうところなので。それをすごく短いスパンで、児童養護施設であれば10年以上という時間をかけるこどももいるんですけれども、自立援助ホームではそれが2年3年、もっと早いこでは半年という中でのスピーディーさは求められるなというところでの入職してからの目まぐるしさにはちょっと戸惑いました。
そうですね、平均で年々入所の時期は長くなってきています。平均すると、1年から1年半ぐらいが平均で退所の時期っていうのは来ています。
この仕事の大変なところは?
私自身の高校時代、大学時代を振り返ってみると。やはり(こどもたちは)外で働いて、お金も入れて、お金も貯めてっていうのをしないといけないんですけれども、それをこどもたちに言わなければいけない。「お金をいっぱい、お金もしっかり貯めていこうね」「お金の使い方も節制しようね」とかっていう部分で、やっぱり一般の家庭と比べてしまうと、本当はこういう生活をするべきではないこどもたちなんだなっていうところを、すごく酷な話をしてしまう。でも、世の中には出していかないといけない、自立させていかなければいけないという思いもあるので、時にはちょっと厳しく言わないといけないっていうところは、こどもたちのバックボーンも見ながらするのは少し、やっぱりいつも勇気というか決意がいるなとは思います。それは日々日々思います。
しんどいというよりかはどちらかというと、それは職務としてしないといけないことなんですけれども、なかなか本来なら強いるべきことでもないやろうなとは思います。
しんどいというよりかはどちらかというと、それは職務としてしないといけないことなんですけれども、なかなか本来なら強いるべきことでもないやろうなとは思います。
この仕事のやりがいは?
本当にこどもたちとの日頃の会話ですね。「今日こんなことあってしんどかったんや」とか、「今日こんなことで褒められたんだ」とか、「俺しんどいけど頑張ってるよな」とか、そういった本当に日常の何気ない会話を積み重ねるのが楽しいですね。別にイベントがあるわけでもないですけれども、その日々日々のこどもたちと話していくと、「この子って前までこういう考え方はできなかったよな」とか、「この子ってやっぱり自信がなかったけど、今すごい自信がついてきてるな」って、そういった小さな変化を会話の中で読み取れる時がやっぱりすごく楽しいし、やってて良かったなと思う時ですね。
子育てとの両立は?
もう妻の存在やとは思いますね。もちろん宿直なので、その時はもう妻が一人でこども達を見ている状況になるので、妻がもう無理ってなったらこの仕事は続けられないかな。なのでその分、やはりお休みの時であったりとか、宿直明けの日であったりっていうのは、家族と一緒に過ごす時間は大切にしています。
子供の家の良いところは?
まず対外的に言うと、男女ホームを男の子も女の子も受け入れしている施設になりますので、なかなか全国を見ても男女ホームっていうのは数が少ないので、その分では需要があるのではないかなと思っています。後は、いわゆる一軒家ではなくて、施設のような形の部分で一人一人の個室があるっていうところで、こども達のプライベートも守られているかなと思います。後は職員層としては福祉をずっとやってきた職員だけではなくて、例えば、よその企業から来られた方もいたり、色々な経歴を持った方がいらっしゃるので、色々な職員の視点を取り入れながらこども達と関われるのが、こども達の支援の幅が広がるかなと思っています。
※撮影当時の情報です。
※撮影当時の情報です。
施設概要

設立当初、神戸市には自立援助ホームがありませんでした。神戸の中で自立援助ホームの認知度が低い中、知ってもらいたいという思いと子どもにとっては頼れるところが1つ増え、人と繋がることが大切だと考えたことから開所されました。
子供の家では、子どもが主体的になり、大人は待つ事が大切なのは大前提とし、大人による導きも同じくらい大切だと思っています。
「一方向で伝える」ではなく「大人からのアドバイス」や「真逆の事を伝える(メリット・デメリット)」を提示して、選択肢を与える事を支援の軸とし、「最終的には自分で決める事」が大切であり、「失敗するのは全然OK」だと考えています。
変化が多い自立援助ホームだからこそ、毎日が職員会議、毎日がケース会議だと思えるくらいとにかく”子ども”も”大人”も話し合いを大事にしています。そういった支援の方針に共感をしてくれる方をお待ちしております!
子供の家では、子どもが主体的になり、大人は待つ事が大切なのは大前提とし、大人による導きも同じくらい大切だと思っています。
「一方向で伝える」ではなく「大人からのアドバイス」や「真逆の事を伝える(メリット・デメリット)」を提示して、選択肢を与える事を支援の軸とし、「最終的には自分で決める事」が大切であり、「失敗するのは全然OK」だと考えています。
変化が多い自立援助ホームだからこそ、毎日が職員会議、毎日がケース会議だと思えるくらいとにかく”子ども”も”大人”も話し合いを大事にしています。そういった支援の方針に共感をしてくれる方をお待ちしております!