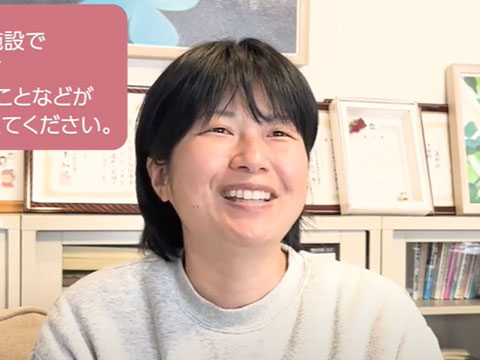アメニティホーム広畑学園 廣島千恵さん
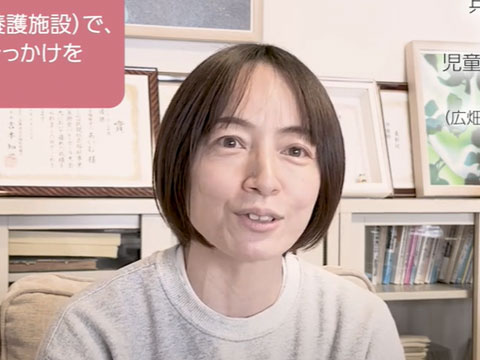
目次
自己紹介をお願いします。
兵庫県姫路市にあります、社会福祉法人あいむの児童家庭支援センター「すみれ」で相談員をしております廣島千恵と申します。
広畑学園(児童養護施設)で、働こうと思ったきっかけを教えてください。
保育士を目指している状況があって、その中で短大の保育科を選んだんですけど、児童養護施設で働けるということをそこで初めて知った際に、親元を離れて何かしらの理由で施設生活をするこどもたちっていうのが、どういう悩みというか、心に傷を負って抱えててっていう部分がすごく気になってっていうところが大学生活を送る中で思ったというのもあって。他の児童養護施設、広畑学園も含めてなんですけど、5、6個ぐらい回ったんですね、自分の中で。その中で広畑学園の実習をさせてもらった際に、玄関先に入ってきた時のお花がもう本当に一面に咲いてて。で、よく言われるのが、このお花って子育てと同じように手をかけて気に掛けてっていう風なことをしないときれいに咲かないんですね。そういうところをきちんとこう咲かせてはるこの雰囲気っていうのに心を打たれたかなというか。
この仕事の魅力や、やりがいはどんなところですか?
最初の3年が幼児の担当だったんですね。その後、7年が小学生で、最後、中学生10年ていう風な形を持たせてもらった時に、年齢が上がれば上がるほど内面的なところのやり取りって目に見えないので、何かその関わりを通して、そのこどもらにこちらの関わりが響いたなと思う瞬間。これは感覚なのでなかなか言葉として表現できにくいところがあるんですけど、それが伝わった、この子と繋がった瞬間が凄くやりがいが一番感じるかなっていうのは、長年してて思うところが大きいですかね。
今は片親ないし両親は必ずいるけれども、事情があっておうちで住めないっていう風なところでお預かりしてる子がもうほとんどなので、またそのバックにいる親御さんが、こどもさんがやっぱり可愛い、でも今は一緒に住めないというところで、その親御さんがもう本当に毎日のように園を訪れてくるっていう。で、こどもが好きであるが故に、何とかこう、こどもを自分の方にっていう風なところで、大分親御さんとのやり取りをした大きいケースがあるんですよ。もう夜中だろうがどこだろうが、やっぱり一緒にいたいっていう風なところを知ったときに、今のこの子にとってその親は大事な存在だし、ずっと繋がっていくものだとは思うんだけれども、一緒にいることで両方が駄目になっちゃうって言うか。だから今ここで、この子が生活する意味というか、その辺のことを、あの頃はだいぶ若くて若いなりにも伝えれる範囲でずっと親御さんにそれを訴えかけてたことがあったんですよ。もうそこまで言うんやったら分かったっていうようなことを言ってくれて、ここに、やっぱり預けてって言うか、もう任せるっていう風なことを言っていただいたぐらいを機に、そのこどももこっちを向き出したというか。バックにいる親御さんと、こっちにいるその職員側がこのこどもにどんな風に育ってほしいかっていう風なところをやり取りを重ねて方向性を一緒にしていくことで、こどもの安定にももちろん繋がりますでしょうし、こどもとの信頼関係も勿論、親御さんとも凄く信頼関係を築いて、うまくいった例があったなっていうのが大きく思い出すんで、何かその辺はやっぱり大きいかなと思います。
今は片親ないし両親は必ずいるけれども、事情があっておうちで住めないっていう風なところでお預かりしてる子がもうほとんどなので、またそのバックにいる親御さんが、こどもさんがやっぱり可愛い、でも今は一緒に住めないというところで、その親御さんがもう本当に毎日のように園を訪れてくるっていう。で、こどもが好きであるが故に、何とかこう、こどもを自分の方にっていう風なところで、大分親御さんとのやり取りをした大きいケースがあるんですよ。もう夜中だろうがどこだろうが、やっぱり一緒にいたいっていう風なところを知ったときに、今のこの子にとってその親は大事な存在だし、ずっと繋がっていくものだとは思うんだけれども、一緒にいることで両方が駄目になっちゃうって言うか。だから今ここで、この子が生活する意味というか、その辺のことを、あの頃はだいぶ若くて若いなりにも伝えれる範囲でずっと親御さんにそれを訴えかけてたことがあったんですよ。もうそこまで言うんやったら分かったっていうようなことを言ってくれて、ここに、やっぱり預けてって言うか、もう任せるっていう風なことを言っていただいたぐらいを機に、そのこどももこっちを向き出したというか。バックにいる親御さんと、こっちにいるその職員側がこのこどもにどんな風に育ってほしいかっていう風なところをやり取りを重ねて方向性を一緒にしていくことで、こどもの安定にももちろん繋がりますでしょうし、こどもとの信頼関係も勿論、親御さんとも凄く信頼関係を築いて、うまくいった例があったなっていうのが大きく思い出すんで、何かその辺はやっぱり大きいかなと思います。
児童家庭支援センターのお仕事内容を教えてください。
大きくその業務として、いわゆる日本全国にある児童家庭支援センターに課せられている業務というのは、大きく5本柱があって、一つはやはり地域に根付いていく事業ということで、月6、7回ですかね、子育て広場っていうことで、すみれの建物の1室を開放してて。そこに親子さんで来られて、保育園とか幼稚園に就園する前にちょっと子育てに対する悩みとかを、親御さんは親御さんでお話ししたり、こどもさんも同じような年齢のこどもさん同士で刺激を受けあいながら、そこで遊びを通して成長していくっていう風な、そういう子育て広場っていうのをさしてもらってるっていうのが大きく地域に根付くっていうところでっていうのがあるんですけど。
2つ目は市からの委託事業っていう市に準じた事業ということで、今大きく養育支援訪問事業と見守り支援強化事業がありまして。地域で生活をしてはる御家庭で、例えば思春期とかを迎えて不登校になってしまったんやっていう悩みも抱えるこどもさんが居はった時に、親御さんがどうそのこどもと向き合っていったらいいんだろうみたいな感じのところで、月何回か行かしていただいて、そこで親御さんの話とか、状況によってはこどもさんにも関われそうだったら話をして、そこで支援をさせていただいているっていうところが一つある。見守り支援強化事業というのは一昨年の11月頃から始まった事業なんですけども、コロナ渦の中でこどもさんが学校に今まで行けてたのに、学校に行きにくくなったりとかして、なかなかこどもさんの現認ができない家庭というのが出てきたんですよね。中身的には食支援ということで、経済的困窮な家庭とか、気になる家庭っていうところを市が把握してはるところに食支援ということで物資を持っていくことで、そのおうちの方のところに少し入ることができて、その物資を渡す中でおうちの様子がちょっと垣間見れたり。そこで出てくる悩みとかを吸い上げて市の方に報告させてもらって、その家の状況を把握していくみたいなところで市に準じた事業というのをさせてもらっているんですね。
3つ目は県の方に応じた事業っていうことで、これは指導委託って言われるものなのですけど。例えばこういう児童養護施設とかに一時保護されたりとかっていう風な形とか、あと、施設入所をしてるこどもさんが状況が整ったんで家庭復帰になりますと。で、家庭復帰をする時に100%安心安全な場所に帰せるかってなるとそこは難しいので、やっぱりこういう課題は残るけれども、以前預かった時よりは改善がしてるということで家庭復帰していくケースが多いんですね。そうなった時に家庭に帰ったからこれで大丈夫ですよではなく、フォローが必要だということで、施設を出た後の支援というところで、暫くはその指導委託っていう形で、こども家庭センターからこの家庭を暫く定期的に訪問して様子を見てほしいっていう形で受けているケースがあるんですけど、そういう事業というのが3つ目。
4つ目は里親支援ですね。今、やっぱりこう施設もだいぶ小規模化されていて、できるだけ地域にっていう風な動きが世の中的にもしてる中で、里親家庭といいつつも、そこに入ってくるこどもさんって施設入所で集団にうまく適応できなかったこどもさんがより個別の方がいいだろうっていうことで、個別に見ていくのに里親家庭に引き取られていく時に、こどもさんそのものは特性があったりとか、関わりにくいこどもさんが非常に多いんですよね。それで里親さんの資格を持っているとは言いつつも、そこでどうこどもに関わっていいのかと行き詰まってくるとは思うので、そこの里親さんへの支援っていう風なところでさしてもらってて。
最後の5つ目は各関係機関との連携っていう風な形で、先程挙げさせていただいたところの事業に対して、こういう風に動かさしてもらったっていうことで、密に報告をさせてもらってたりっていうこともそうですし。要保護児童対策地域協議会っていうのが多分どこにもあると思うんですけど、月一回「ここの地域では今こういうケースがあります」っていう会議が定期的に行なわれるんですね。そこにもすみれとして参加させてもらってて。そこで情報共有したり、実際にそこの中で見守りに行かせてもらってるケースとかも上がってくるので。そういう連携みたいなところも大きく、児童家庭支援センターが担う業務の一つにはなっています。
2つ目は市からの委託事業っていう市に準じた事業ということで、今大きく養育支援訪問事業と見守り支援強化事業がありまして。地域で生活をしてはる御家庭で、例えば思春期とかを迎えて不登校になってしまったんやっていう悩みも抱えるこどもさんが居はった時に、親御さんがどうそのこどもと向き合っていったらいいんだろうみたいな感じのところで、月何回か行かしていただいて、そこで親御さんの話とか、状況によってはこどもさんにも関われそうだったら話をして、そこで支援をさせていただいているっていうところが一つある。見守り支援強化事業というのは一昨年の11月頃から始まった事業なんですけども、コロナ渦の中でこどもさんが学校に今まで行けてたのに、学校に行きにくくなったりとかして、なかなかこどもさんの現認ができない家庭というのが出てきたんですよね。中身的には食支援ということで、経済的困窮な家庭とか、気になる家庭っていうところを市が把握してはるところに食支援ということで物資を持っていくことで、そのおうちの方のところに少し入ることができて、その物資を渡す中でおうちの様子がちょっと垣間見れたり。そこで出てくる悩みとかを吸い上げて市の方に報告させてもらって、その家の状況を把握していくみたいなところで市に準じた事業というのをさせてもらっているんですね。
3つ目は県の方に応じた事業っていうことで、これは指導委託って言われるものなのですけど。例えばこういう児童養護施設とかに一時保護されたりとかっていう風な形とか、あと、施設入所をしてるこどもさんが状況が整ったんで家庭復帰になりますと。で、家庭復帰をする時に100%安心安全な場所に帰せるかってなるとそこは難しいので、やっぱりこういう課題は残るけれども、以前預かった時よりは改善がしてるということで家庭復帰していくケースが多いんですね。そうなった時に家庭に帰ったからこれで大丈夫ですよではなく、フォローが必要だということで、施設を出た後の支援というところで、暫くはその指導委託っていう形で、こども家庭センターからこの家庭を暫く定期的に訪問して様子を見てほしいっていう形で受けているケースがあるんですけど、そういう事業というのが3つ目。
4つ目は里親支援ですね。今、やっぱりこう施設もだいぶ小規模化されていて、できるだけ地域にっていう風な動きが世の中的にもしてる中で、里親家庭といいつつも、そこに入ってくるこどもさんって施設入所で集団にうまく適応できなかったこどもさんがより個別の方がいいだろうっていうことで、個別に見ていくのに里親家庭に引き取られていく時に、こどもさんそのものは特性があったりとか、関わりにくいこどもさんが非常に多いんですよね。それで里親さんの資格を持っているとは言いつつも、そこでどうこどもに関わっていいのかと行き詰まってくるとは思うので、そこの里親さんへの支援っていう風なところでさしてもらってて。
最後の5つ目は各関係機関との連携っていう風な形で、先程挙げさせていただいたところの事業に対して、こういう風に動かさしてもらったっていうことで、密に報告をさせてもらってたりっていうこともそうですし。要保護児童対策地域協議会っていうのが多分どこにもあると思うんですけど、月一回「ここの地域では今こういうケースがあります」っていう会議が定期的に行なわれるんですね。そこにもすみれとして参加させてもらってて。そこで情報共有したり、実際にそこの中で見守りに行かせてもらってるケースとかも上がってくるので。そういう連携みたいなところも大きく、児童家庭支援センターが担う業務の一つにはなっています。
児童養護施設での経験は今の仕事にどのように影響しているか教えてください。
先程自分達が見てきたこどもの話をした中でいろんなこどもさんがいたと思うんですけど、でもその子達ってもう成人もして、早いこどもはね、もうこどもを持っているんですね。その時にもう地域に入ってるんですよ。親となった卒園生のこども達が自分のこどもを産んだ時に抱えにくさとか生きづらさとかっていうのを感じた時に、その当時のことも分かっている職員で、なおかつ今地域に根差した支援をさせてもらう立場としては、そこの関わりまでできるっていうのは、児童養護で育ったこども達が、いずれはどの子もそうだと思うんですけど、地域に入っていった時の困りとかを感じた時に助けを求めていける場所っていう風なことを思った時に、その児童養護にいた時の職員としての関わりっていう風なところを生かせる形にも今はすごくなっているかなっていうのは大きいと思います。
最後に一言、メッセージをお願いします。
今、私は児童家庭支援センター「すみれ」で相談員として働いているんですけど、やっぱりそのベースになったものというのがアメニティホーム広畑学園での経験かなっていう風なことを思っているので、ぜひとも広畑学園の方にいらしてください。
※撮影当時の情報です
※撮影当時の情報です
施設概要

アメニティホーム広畑学園は兵庫県姫路市にある児童養護施設です。
住宅街の中にありながら、自然あふれる広い敷地の中でのびのびと子どもたちが生活しています。
子どもたち一人ひとりの成長や発達に合わせて、日常や生活リズムを大切にした養育を実践し、自立に向けた力を育んでいます。
戦災孤児の受け入れから始まった広畑学園ですが、時代や世情のニーズに合わせた柔軟な運営を行い70年を超える歴史が有ります。
住宅街の中にありながら、自然あふれる広い敷地の中でのびのびと子どもたちが生活しています。
子どもたち一人ひとりの成長や発達に合わせて、日常や生活リズムを大切にした養育を実践し、自立に向けた力を育んでいます。
戦災孤児の受け入れから始まった広畑学園ですが、時代や世情のニーズに合わせた柔軟な運営を行い70年を超える歴史が有ります。