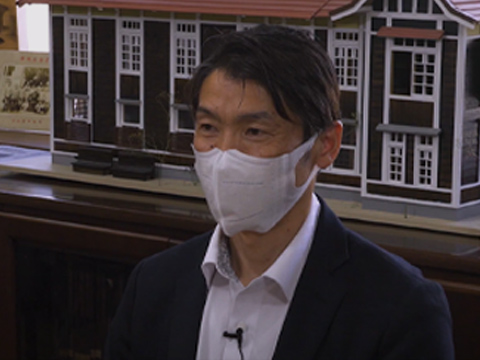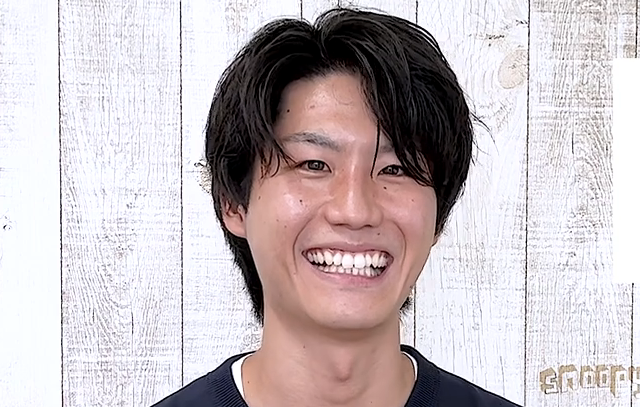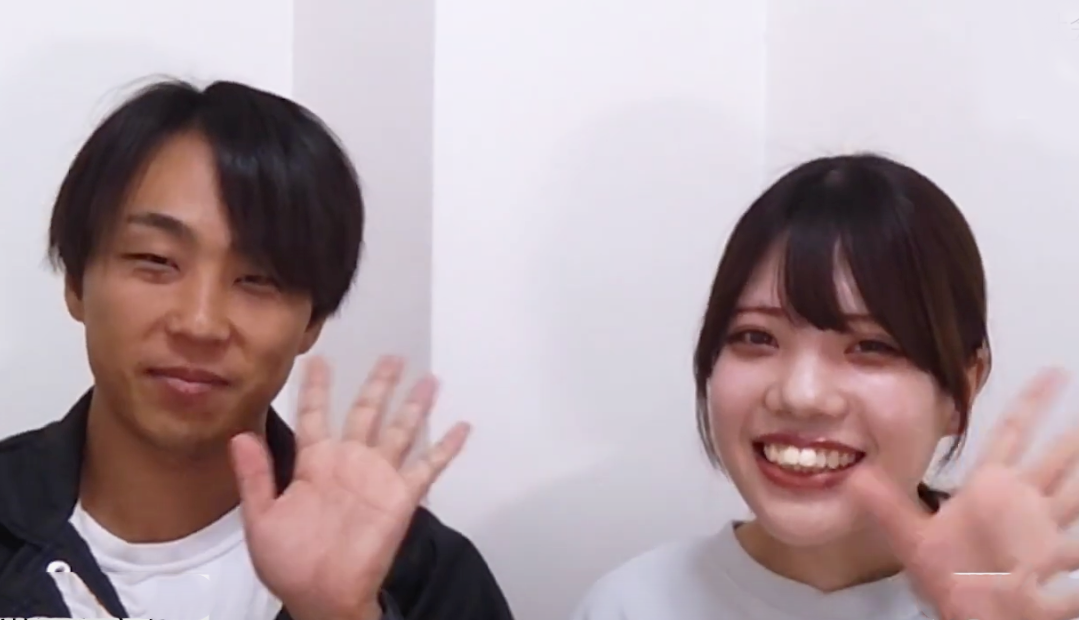武田塾 枡田俊介さん
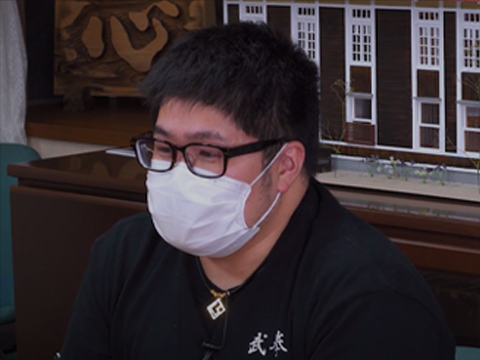
児童養護施設で働くきっかけ
僕はそもそも大学が体育の教員免許を取れるところで、免許取って1年間は生徒指導サポートの方をしてたんですけど、そこでも面白くて。こんな見た目なんで、やんちゃな子ら、ちょっとこう授業から外れて日向ぼっこしてる子らといつも話してて。で、何で入れへんねやって話をしたら、まあ、今入ってもどうせ教師には「もうどいとけ」とか、「もううるさい」という話をされるからっていう話で。ただ、体育の授業は1年2年3年関係なしに全部入って1年から6年まで体育やってるような子らやったんですけど、その子らと話してたら悪い子らではないというか、おもしろい子らやなと思いながら、ただ現状的にはやっぱりこうクラスに入らないし、入れない子たちやったんで。それを見ててちょっと教師になるっていうのは僕の中では違うかなっていうのを感じて。それでハローワークで教員免許を活かせる仕事ないかなっていうところで、見に行かせてもらった時に、たまたまハローワークの受付の方が児童養護施設の職員やったんです、元々。本当にたまたまやったんですけど。で、「君、児童養護施設の職員とか向いてるんじゃないかな」っていう話をされて、教員課程で児童養護施設の事をほとんど学ばないんで、僕は正直、昔やってたキッズウォーぐらいの、あんなん確かあったなみたいな感じやったんですけど。そこから結局、児童養護施設ってこうなんだよという話をされて、「親の代わりですよね」って言った時に印象に残ってるのは、「親ではない、親には絶対なられへん」っていう言葉で、すごい面白そうだなというので、その時もう5月6月の話やったんで、その時に募集を掛けてたのが武田塾やったっていう。
取り敢えず児童養護施設は、母体は全部一緒じゃないですか、だから児童養護施設で働くってことを経験として、どこでもいいかなって。働くところは変わらんかなと思って。
取り敢えず児童養護施設は、母体は全部一緒じゃないですか、だから児童養護施設で働くってことを経験として、どこでもいいかなって。働くところは変わらんかなと思って。
児童養護施設でのやりがいと苦労について
苦労もやりがいも多分一緒やと思うんすけど、考えるところですかね。こどもたちに何をしてあげられるかって正直、僕は何にもできないんで。僕たち大人(職員)は、学生から上がって社会人経験したことなくて、ここで社会人初めての子が1人暮らしもしてなくて、実家住まいやったりしてる子らが施設の子に何を教えてあげられるんやっていったら、まあ大したこと教えられないよねって。ただ何かこう大人になった時に、「ああ、あいつ何か言ってたな」ぐらい思っといてくれるような形で、そう思えるようにどういう声掛けをしたらいいかとか、どういう行動に目をつけたらいいかとかを日々考えてますかね。
職員の専門性みたいなところがどうしても言われてる中で、うちの施設でもケースとか、生い立ち・成育歴っていうものがありますけど、どこの施設でも多分あると思うんすけど、それを見てうちの職員が、「いや、こんなん見たくなかった」っていうことを言ってた子がいたんですけど、でも職員としては当たり前じゃないですか。例えばケースワーカーさんとかそんな当たり前。でも、その子の意見は一般論だと思うんです。自分の生い立ちをこう紙に書いて、じゃあ見てくれ、共有してくださいって言うと嫌じゃないですか。それ一般論で、いや職員の専門性って何ですかって言われた時に、「生い立ち見て、だから今の行動を見て、先を考える」っていう、この一貫した流れがすごい大切なんやろうなっていうのが、それが僕たちのやりがいでもあり、専門性であり、ただそれがしんどさでもあるというかっていうのを思いましたかね。
思い入れが深い子。僕はずっと高校生担当なので、もう入った時が高校生担当だったんで、高校生みんな思い入れはあるのはありますね。あとはその僕、活動で武拳会というキックボクシング部してるんですど、上級生とか選手コースの子らはやっぱみんな思い入れはありますね。その中で特にって言われると、2、3年前に卒業した子で支援学校に通ってた子がいたんですけど、その子がまず僕に格闘技を教えてほしいって言ってきたのがはじめで、こういう武拳会が成り立って。その子が中学校でも友達学級に入ってて、その子がもう何て言うんですかね、ここで違いを結構してて、そこで、2年目になって格闘技を教えてほしいっていう話をしにきて、そこから自分ら二人でやってたのが、だんだん周りがこういっぱい集まってきて、俺も教えてほしいっていう子らが増えてきて。当時の施設長からは、部にしたら部費が出るんじゃないかっていう話をされて部活動になって、それで武田拳闘部っていうものから、外に試合に行けるようになったので、武拳会っていう会派に改名したっていう。その子が卒業する時にプロになった子なので。外のポスターとかにも載ってるその子が中3の時に「俺はバイトはできへん」と。俺は支援学校やからバイトはできへん。だから、プロで金稼ぐんやって言ってて、それがほんまに実現したっていう。本当にすごい子やったかなと。そこから始まったんで、その子がプロになったことで、他の今の子らが自分もプロになりたいって目標が、例えば施設でプロになった子がいてなかったら、ただの夢で笑われるかもしれんけど、うちやったらプロになった子が実際にいるんで、目標に変わって。なれる。なった子がいる。っていう実績があるんで、だからそこがすごいうちにとっては大きかった。その子も一番大きかったかなと。今の子も思い入れはありますけど。
職員の専門性みたいなところがどうしても言われてる中で、うちの施設でもケースとか、生い立ち・成育歴っていうものがありますけど、どこの施設でも多分あると思うんすけど、それを見てうちの職員が、「いや、こんなん見たくなかった」っていうことを言ってた子がいたんですけど、でも職員としては当たり前じゃないですか。例えばケースワーカーさんとかそんな当たり前。でも、その子の意見は一般論だと思うんです。自分の生い立ちをこう紙に書いて、じゃあ見てくれ、共有してくださいって言うと嫌じゃないですか。それ一般論で、いや職員の専門性って何ですかって言われた時に、「生い立ち見て、だから今の行動を見て、先を考える」っていう、この一貫した流れがすごい大切なんやろうなっていうのが、それが僕たちのやりがいでもあり、専門性であり、ただそれがしんどさでもあるというかっていうのを思いましたかね。
思い入れが深い子。僕はずっと高校生担当なので、もう入った時が高校生担当だったんで、高校生みんな思い入れはあるのはありますね。あとはその僕、活動で武拳会というキックボクシング部してるんですど、上級生とか選手コースの子らはやっぱみんな思い入れはありますね。その中で特にって言われると、2、3年前に卒業した子で支援学校に通ってた子がいたんですけど、その子がまず僕に格闘技を教えてほしいって言ってきたのがはじめで、こういう武拳会が成り立って。その子が中学校でも友達学級に入ってて、その子がもう何て言うんですかね、ここで違いを結構してて、そこで、2年目になって格闘技を教えてほしいっていう話をしにきて、そこから自分ら二人でやってたのが、だんだん周りがこういっぱい集まってきて、俺も教えてほしいっていう子らが増えてきて。当時の施設長からは、部にしたら部費が出るんじゃないかっていう話をされて部活動になって、それで武田拳闘部っていうものから、外に試合に行けるようになったので、武拳会っていう会派に改名したっていう。その子が卒業する時にプロになった子なので。外のポスターとかにも載ってるその子が中3の時に「俺はバイトはできへん」と。俺は支援学校やからバイトはできへん。だから、プロで金稼ぐんやって言ってて、それがほんまに実現したっていう。本当にすごい子やったかなと。そこから始まったんで、その子がプロになったことで、他の今の子らが自分もプロになりたいって目標が、例えば施設でプロになった子がいてなかったら、ただの夢で笑われるかもしれんけど、うちやったらプロになった子が実際にいるんで、目標に変わって。なれる。なった子がいる。っていう実績があるんで、だからそこがすごいうちにとっては大きかった。その子も一番大きかったかなと。今の子も思い入れはありますけど。
武拳会について
うちで今武拳会っていうのがあって、武田拳闘部っていう部活動から、今年武拳会に改名して。今までは外のキックボクシングジムに何名か通わせて、そこで試合に出るっていう流れやったんです。ただ、措置費とか限界があったり、運営指針でも「可能な限り」(と書かれていた)。「可能な限り」のうちの限界が2名とか3名。それで結局、お金の話じゃないけど、40万50万が年間で掛かるので、結局そこに掛かった分、他のこどもには掛けられないよねっていうのが、それが運営指針の可能な限りっていうとこなんだよな。頑張ってる子はいっぱいいるんで。
うちフットサル部とかあるんですけど、もちろんそれでも頑張ってる子はいてるんで、ただ頑張ってる子にちゃんとピックアップが当たるようにっていうところで、今年から僕もいろんなアマチュアの大会の人に連絡を取って、今年からT.B.NATION CUP!っていうアマチュアのキックボクシングの大会に出れるようになって、今のところDクラスとかCクラスですけど4戦して4勝なんで、もうここでやってることが他の外の格闘技ジムと遜色ないとは言わないですけど、一定のレベルを達成したっていうことが認められたことかなと思ってます。
(インタビュアー)3つの種類に分かれているんですよね。
まず1個はフィットネスで、これは対人練習は怖いと。顔にもらったりは怖い、ただ体を動かしたいっていう子らのコースで、チャレンジコースってのが、対人になって試合に出場したいっていう子らのコースで、試合に出場できるように頑張っていくコース。選手コースは、今の時点でもう試合にも出ていけるし、もう試合に勝っていける。出ることが目標じゃなくて勝つことが目標のコースの、その3コースに分かれてます。
基本的に選手コースの子たちには、自分達の練習とチャレンジとフィットネスのコースの教える指導員としての役割も兼ねて、選手コースに上がれるか上がれないかっていうのを判断しています。自分が強かったらいいだけじゃない。でないと下が育たない。下を育てるのをね、部活動で言ったら、やっぱり先輩らの役目かなとは思うので、そういう形でなおかつ育てる。あと責任感と、自分が教えてもらったりインプットしたことをちゃんとアウトプットできる機会を作るっていうのが。
(インタビュアー)選手コースに上がるための試験はあるんですか?
いや試験はないです。選手コースの子らと話して、例えばチャレンジコースで頑張ってたり、試合にも勝ってたりで、あと教えれるのかっていうところを評価して、上に上がる時に基準っていうのはないですけど、別に空手ではないので基準もないですけど、そこで選手コースの子らと話をして、「もうそろそろ上がれるんじゃない?」。だから実際落とした子もいます、選手コースから。落とした経験もありますね。
それこそ来へんかったり、バイトとかしてるんで、高校生はどうしても来れない時もありますけど、実際試合出すって言った時にあの子の名前、僕は言わなかったんで。あの子めっちゃ号泣して、ただ、自分が呼ばれへん理由も分かってる。練習にもあんまり行かれへんかったし、僕は日頃の行いもいろんなポイントで見ているから、それを言われへんのもよく分かってるって言ってたみたいで。
うちフットサル部とかあるんですけど、もちろんそれでも頑張ってる子はいてるんで、ただ頑張ってる子にちゃんとピックアップが当たるようにっていうところで、今年から僕もいろんなアマチュアの大会の人に連絡を取って、今年からT.B.NATION CUP!っていうアマチュアのキックボクシングの大会に出れるようになって、今のところDクラスとかCクラスですけど4戦して4勝なんで、もうここでやってることが他の外の格闘技ジムと遜色ないとは言わないですけど、一定のレベルを達成したっていうことが認められたことかなと思ってます。
(インタビュアー)3つの種類に分かれているんですよね。
まず1個はフィットネスで、これは対人練習は怖いと。顔にもらったりは怖い、ただ体を動かしたいっていう子らのコースで、チャレンジコースってのが、対人になって試合に出場したいっていう子らのコースで、試合に出場できるように頑張っていくコース。選手コースは、今の時点でもう試合にも出ていけるし、もう試合に勝っていける。出ることが目標じゃなくて勝つことが目標のコースの、その3コースに分かれてます。
基本的に選手コースの子たちには、自分達の練習とチャレンジとフィットネスのコースの教える指導員としての役割も兼ねて、選手コースに上がれるか上がれないかっていうのを判断しています。自分が強かったらいいだけじゃない。でないと下が育たない。下を育てるのをね、部活動で言ったら、やっぱり先輩らの役目かなとは思うので、そういう形でなおかつ育てる。あと責任感と、自分が教えてもらったりインプットしたことをちゃんとアウトプットできる機会を作るっていうのが。
(インタビュアー)選手コースに上がるための試験はあるんですか?
いや試験はないです。選手コースの子らと話して、例えばチャレンジコースで頑張ってたり、試合にも勝ってたりで、あと教えれるのかっていうところを評価して、上に上がる時に基準っていうのはないですけど、別に空手ではないので基準もないですけど、そこで選手コースの子らと話をして、「もうそろそろ上がれるんじゃない?」。だから実際落とした子もいます、選手コースから。落とした経験もありますね。
それこそ来へんかったり、バイトとかしてるんで、高校生はどうしても来れない時もありますけど、実際試合出すって言った時にあの子の名前、僕は言わなかったんで。あの子めっちゃ号泣して、ただ、自分が呼ばれへん理由も分かってる。練習にもあんまり行かれへんかったし、僕は日頃の行いもいろんなポイントで見ているから、それを言われへんのもよく分かってるって言ってたみたいで。
職員さんの武拳会参加について
僕はこどももそうですし、職員もそうですし、強制的に入れた子は誰もいない。今集まってくれた子はみんな自分らで、こどももそうですし、大人もそうですし、僕が強制したことがないですね。大人も3人いるんです。男性1人と、女性2名がいてるんですけど、女性の1人はフィットネスで、男性と女性の1人はチャレンジコースに入ってるんですけど、もう男性の1年目の子は、1年目ってことはもう23歳なんで、もう5月試合出る。
(インタビュアー)成人の部で試合に出るということですよね。それは武拳会のメンバーとして出るってことですか?
はい、そうです。
(インタビュアー)本当に珍しくてびっくりします。こういう風に一緒にこども達と目標に向かって頑張るってこと自体は、、どこの施設もいろんな行事とかあったりすると思うんですけど、それを職員と一緒にやるみたいなところで、格闘技だったり、部活だから良かったなとか、職員が教えるってことがやはり良かったなとか、その辺りどうですか?
職員が教えるってことは一番大切だと思います。結局、キックボクシングのジム行ったらキックボクシングできますし、柔道行ったら柔道できますし、それは外で教えた方が上手なりますし。もちろん専門なんで。僕は専門じゃないんで、強くなるかは分かんないですけど。ただ、日常場面と照らし合わせて、こどもの動きやったり、見た時に「ああ、今悩んでんな」とか。練習を見て、今悩んでんなとか練習けえへんかったりして、昨日のことがあれやろうなとかいうところは、児童養護施設でやる部活動にとってすごい大切なことだと思います。
たぶん、それ一貫して見た時にまた支援に広がっていくんちゃうかなって思いますけど。要は格闘技行ったって、それはそれで大切だと思います。外の社会で、「そんなん知らんわ」「児童養護施設に居るからなんや」っていうのも大切だと思います。ただ、もちろんそれだけじゃ支援は広がらないんで。外に行って、児童養護施設が何やっていうのは、それだけ。それ以外では広がらないんで、指導員、指導者がどういう目線で物事を考えて支援とつなげて、なおかつこどもの力考えて、考える力をあげてっていうことがどれだけ大切かっていうのは、やっぱ職員が教えるってことに圧倒的に意味があると思います。
(インタビュアー)今一緒にやってる女性の職員さん二人いましたけど、あの二人は教えるっていうか、まずは一緒に頑張るってことですよね。
もちろん。教えられるレベルではないので。男性職員もやったことないので。だからこう、自分の担当の中学2年生の子とやったら、ボコボコにされたりするんで。でもそれがやっぱりこどもにとっては嬉しいことでもあるというか、大人がいつでも強い時代じゃないよっていう。頑張れば頑張った奴が、ちゃんと評価成果が出るっていうところがあるんで。体格とかはもちろん違ってくるかもしれんけど、こどもが大人に勝ったっていいじゃないですか。
(インタビュアー)成人の部で試合に出るということですよね。それは武拳会のメンバーとして出るってことですか?
はい、そうです。
(インタビュアー)本当に珍しくてびっくりします。こういう風に一緒にこども達と目標に向かって頑張るってこと自体は、、どこの施設もいろんな行事とかあったりすると思うんですけど、それを職員と一緒にやるみたいなところで、格闘技だったり、部活だから良かったなとか、職員が教えるってことがやはり良かったなとか、その辺りどうですか?
職員が教えるってことは一番大切だと思います。結局、キックボクシングのジム行ったらキックボクシングできますし、柔道行ったら柔道できますし、それは外で教えた方が上手なりますし。もちろん専門なんで。僕は専門じゃないんで、強くなるかは分かんないですけど。ただ、日常場面と照らし合わせて、こどもの動きやったり、見た時に「ああ、今悩んでんな」とか。練習を見て、今悩んでんなとか練習けえへんかったりして、昨日のことがあれやろうなとかいうところは、児童養護施設でやる部活動にとってすごい大切なことだと思います。
たぶん、それ一貫して見た時にまた支援に広がっていくんちゃうかなって思いますけど。要は格闘技行ったって、それはそれで大切だと思います。外の社会で、「そんなん知らんわ」「児童養護施設に居るからなんや」っていうのも大切だと思います。ただ、もちろんそれだけじゃ支援は広がらないんで。外に行って、児童養護施設が何やっていうのは、それだけ。それ以外では広がらないんで、指導員、指導者がどういう目線で物事を考えて支援とつなげて、なおかつこどもの力考えて、考える力をあげてっていうことがどれだけ大切かっていうのは、やっぱ職員が教えるってことに圧倒的に意味があると思います。
(インタビュアー)今一緒にやってる女性の職員さん二人いましたけど、あの二人は教えるっていうか、まずは一緒に頑張るってことですよね。
もちろん。教えられるレベルではないので。男性職員もやったことないので。だからこう、自分の担当の中学2年生の子とやったら、ボコボコにされたりするんで。でもそれがやっぱりこどもにとっては嬉しいことでもあるというか、大人がいつでも強い時代じゃないよっていう。頑張れば頑張った奴が、ちゃんと評価成果が出るっていうところがあるんで。体格とかはもちろん違ってくるかもしれんけど、こどもが大人に勝ったっていいじゃないですか。
新しい取り組みについて
武拳会で、こどもたちがメインとなってInstagramの運営をしたいと思ってまして。
Instagramをすることでこどもたちが記事を考えて、写真の撮り方。要は、こどもがここに居るっていう、入所してるっていうところを写してはいけないとかいう、そういう決まりがあるので、写真の撮り方、「じゃあ、この足だけやったらいいか」とか、「道具だけやったらいいか」「その日に何を載せるのか」「どういう記事を載せるのか」っていうのを、物事を考える力というところとか。あとはInstagramを運営することによって、措置費で賄えない武拳会の活動費をちゃんと助成いただいたり、寄付いただいたりして、その寄付をいただいた会社をしっかりInstagramでも報告して、「いただきました。ありがとうございます。」とかいうところを、要はお金を稼いだり、お金のやりとりをするっていうのを、高校からしっかり学ぶっていうところで、SNSっていうのはもう社会情勢の中でも必須アイテムになってるんで、それの使い方を知らない高校生やったり、中学生ぐらいで。もう今は多分一般的なところではどこも誰でもやってる。でも、それがやっぱり児童養護施設だったら不安とか怖いとかいう部分があるので、それをちゃんと学んで、しっかりと教えられるように、また外に発信できるように自分たちの活動をちゃんと評価してもらって、僕たち、こんなこれやってんねんていうのをちゃんと社会的に評価される舞台をちゃんとして、最終的にはこの子らが自立した時に、保護者がいないお子さんもいるので、自分で考えて、自分で育つっていう力を身につけるためにInstagramの運営をしようと思ってます。
こういう児童養護施設の特徴として、例えば格闘技ジム、キックボクシングジムではInstagramとかFacebookとかやってはるとこあるけど、それはもう活動の報告をやったりで、館長さんがやってたり、その担当がやってたりっていうのがあると思うんですが、うちはこどもたちと一緒に応援して一緒にやっていくっていうところをメインに、今、それを考えてやってます。こどもたちが主体となってやるところって聞いたことないですね。職員がやるっていうのはちょっとずつ出てきましたね。各職員個人でやってはる人はいっぱいいますけど、施設としてそもそもSNSを利用するっていうこともないじゃないですか。だからむしろSNSをやって、気質気風とか、まだ児童養護施設ってみんな「児童養護施設はこうじゃないとあかん」とか色々あると思うんで、それがもうちゃんと自分たちがやってる活動にちゃんと協力してくれる人を募るっていう形で、それだけ本気なんやでっていうことをちゃんと発信できるのは大切だと思うんで。施設側とかも大切だと思いますけど、ちゃんとね、自分たちがやってることをこどもたちを主体に考えることが、僕は必要かなと思います。
Instagramをすることでこどもたちが記事を考えて、写真の撮り方。要は、こどもがここに居るっていう、入所してるっていうところを写してはいけないとかいう、そういう決まりがあるので、写真の撮り方、「じゃあ、この足だけやったらいいか」とか、「道具だけやったらいいか」「その日に何を載せるのか」「どういう記事を載せるのか」っていうのを、物事を考える力というところとか。あとはInstagramを運営することによって、措置費で賄えない武拳会の活動費をちゃんと助成いただいたり、寄付いただいたりして、その寄付をいただいた会社をしっかりInstagramでも報告して、「いただきました。ありがとうございます。」とかいうところを、要はお金を稼いだり、お金のやりとりをするっていうのを、高校からしっかり学ぶっていうところで、SNSっていうのはもう社会情勢の中でも必須アイテムになってるんで、それの使い方を知らない高校生やったり、中学生ぐらいで。もう今は多分一般的なところではどこも誰でもやってる。でも、それがやっぱり児童養護施設だったら不安とか怖いとかいう部分があるので、それをちゃんと学んで、しっかりと教えられるように、また外に発信できるように自分たちの活動をちゃんと評価してもらって、僕たち、こんなこれやってんねんていうのをちゃんと社会的に評価される舞台をちゃんとして、最終的にはこの子らが自立した時に、保護者がいないお子さんもいるので、自分で考えて、自分で育つっていう力を身につけるためにInstagramの運営をしようと思ってます。
こういう児童養護施設の特徴として、例えば格闘技ジム、キックボクシングジムではInstagramとかFacebookとかやってはるとこあるけど、それはもう活動の報告をやったりで、館長さんがやってたり、その担当がやってたりっていうのがあると思うんですが、うちはこどもたちと一緒に応援して一緒にやっていくっていうところをメインに、今、それを考えてやってます。こどもたちが主体となってやるところって聞いたことないですね。職員がやるっていうのはちょっとずつ出てきましたね。各職員個人でやってはる人はいっぱいいますけど、施設としてそもそもSNSを利用するっていうこともないじゃないですか。だからむしろSNSをやって、気質気風とか、まだ児童養護施設ってみんな「児童養護施設はこうじゃないとあかん」とか色々あると思うんで、それがもうちゃんと自分たちがやってる活動にちゃんと協力してくれる人を募るっていう形で、それだけ本気なんやでっていうことをちゃんと発信できるのは大切だと思うんで。施設側とかも大切だと思いますけど、ちゃんとね、自分たちがやってることをこどもたちを主体に考えることが、僕は必要かなと思います。
学生さんへメッセージ
福祉自体をどう学んでいるかちょっと分かんないんですけど、僕はずっと言ってるんですけど、職業病かもしれないですけど、うちの職員でも言ってて、休みでも「今日寒いな」って思ったら、あの子らはちゃんと上着着ていったかなとか、自分の服買いに行ったのに「ああ、これあの子に似合いそう」みたいなことを言うことが、それがいいかわかんないですけど、休みの時までって言われたらそうだけど、それぐらい思いを持ってできる子はすごい児童養護施設が魅力に感じると思います。だから、こどものために、とりあえずはこどものために何かしてあげたいって思うことが大切かなって。もうそれで多分入って現実を示されて、その行動が何なのかっていうのを考えるのが僕たちの専門性だと思うので、ぜひ児童養護施設の職員になってほしいと思います。
※撮影当時の情報です。
※撮影当時の情報です。
施設概要

「心の座談会」
3年目までの職員に対して、心理士と同期職員で集まる機会を月1回作っています。子どものことや仕事で不安な事など、ざっくばらんに話しをします。生活支援を担うと集まる機会も少ないので、同期職員の繋がりも大切にしています!!
「常時2名勤務」
勤務体制として、常時2名勤務を目指しております。一人勤務という児童養護施設の勤務形態を払拭し、子どものことを考えられるように取り組んでいます。
「武拳会」
他施設では聞いたことがない取り組みとして、キックボクシング部が存在します。「選手コース」「チャレンジコース」「フィットネスコース」の3コースに分けて、月~金の週5回練習に励んでいます。選手コースの子ども達が他コースを指導する仕組みを作り、主体性を養うことを目標としています。今年度より、職員の入会も募集しております。ぜひ!
「武田フットサル部」
過去には近畿大会に出場したこともあります。現在、活動日を土曜日・日曜日と固定し、監督1名・コーチ2名と共に大阪府予選突破、近畿大会出場を目指し、練習に励んでおります。
「インターシップ交流会」
大阪府中小企業家同友会の協力のもと月1回開催しています。子ども達が働くイメージを付けられるように小学生は物づくり、中高生は同友会の方々と自分のやりたい仕事や今の心情について話をします。
3年目までの職員に対して、心理士と同期職員で集まる機会を月1回作っています。子どものことや仕事で不安な事など、ざっくばらんに話しをします。生活支援を担うと集まる機会も少ないので、同期職員の繋がりも大切にしています!!
「常時2名勤務」
勤務体制として、常時2名勤務を目指しております。一人勤務という児童養護施設の勤務形態を払拭し、子どものことを考えられるように取り組んでいます。
「武拳会」
他施設では聞いたことがない取り組みとして、キックボクシング部が存在します。「選手コース」「チャレンジコース」「フィットネスコース」の3コースに分けて、月~金の週5回練習に励んでいます。選手コースの子ども達が他コースを指導する仕組みを作り、主体性を養うことを目標としています。今年度より、職員の入会も募集しております。ぜひ!
「武田フットサル部」
過去には近畿大会に出場したこともあります。現在、活動日を土曜日・日曜日と固定し、監督1名・コーチ2名と共に大阪府予選突破、近畿大会出場を目指し、練習に励んでおります。
「インターシップ交流会」
大阪府中小企業家同友会の協力のもと月1回開催しています。子ども達が働くイメージを付けられるように小学生は物づくり、中高生は同友会の方々と自分のやりたい仕事や今の心情について話をします。